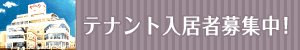このままでいいんや、このまま幸せになるんや
1995年春、兵庫県西宮市。脳性麻痺の娘 望美(5歳)を抱え介護に勤しむ美幸(38歳)は、望美の世話をできるのは自分だけと、介護に、家事に、子育てに、家の中のことを全て背負っていた。次第に追い詰められていった美幸は、長年会っていない大分に住む母 喜子(65歳)に支援を頼む。「そげな子は、自分で育てられるわきゃないき! こっちはこっちの生活があるんやけん!」意を決し助けを求めた美幸に対し、母親の言葉は残酷だった。
見えないストレスを抱えた美幸は、見た目は元気ながらも不眠と摂食障害に悩む‟仮面うつ”を患ってしまう。そんな疲れきった毎日で、美幸は“望美がいなかったら幸せだった…”という自分の無思慮な考えにハッとするが、次の瞬間、美幸の脳裏には、同じ団地に住み、いつも母親のようにしてくれている 大守(83歳)に言われた言葉が浮かんだ。「全ては自分やからね」望美のせいじゃない。全ては自分次第だ。そう思った美幸はもう一度、自分らしい生き方を取り戻すべく、夢だった児童文学者への道を目指し、小説を書きはじめる。しかし、美幸が前向きになり、暗闇から抜け出そうと決めた途端、美幸の前に新たな試練が襲ってくる。母の喜子が認知症とうつ病を併発してしまったのだ…。
「死にたい」と訴える母に、手を差し伸べる気がおきない美幸。本当に困っている時に助けてくれなかった母を、そう簡単に助けたいとは思えない。だが、子どもの頃の懐かしい記憶をたどれば、親子の距離はそう遠いものではなかった――。
「葉書100枚ください!」
美幸は、郵便局で大量の葉書を購入。母に向けて「くすっ」と笑える日々の話を書いて送ることにした。毎日を少しでも、明るくするような出来事を書いて送る。それは、将来が見通せず暗闇で怯えているかもしれない母の心に、灯をつけたい一心からであった。
私の葉書を待っていてほしい。明日の朝も、明後日の朝もずっと生きていてほしい。美幸は、毎日かかさず葉書を出し続けた…。